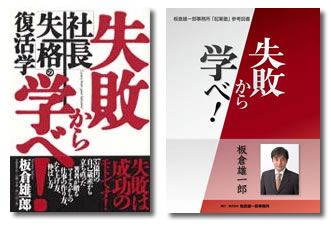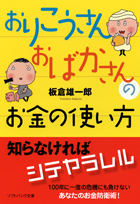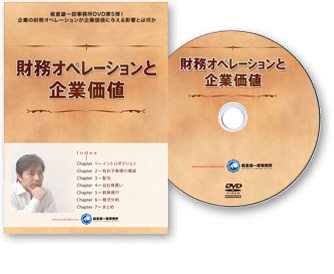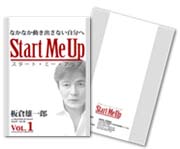(毎週火・木・土曜日は、パートナーエッセイにお付き合いください。)
皆さんこんにちは、パートナーの石野雄一です。
今回は、ファイナンス基礎理論の番外編と称して、
有利子負債の節税効果について、
お話してみたいと思います。
ちょっと、基礎とはいえない内容かも知れませんが、
最後までおつき合いください。
ここにU社とL社があるとします。
営業利益は、どちらの会社も50百万円です。
U社には、有利子負債はありません。
一方で、L社は、100百万円を年率10%で借入しています。
資本構成以外は、全く同じ内容の会社であると考えてください。
ここでは、業績は資本構成の影響を受けず、
法人税率は40%とします。
このとき、損益計算書は、次のようになります。
厳密にいえば、税引後利益とキャッシュフローは違いますが、
ここでは同じとします。
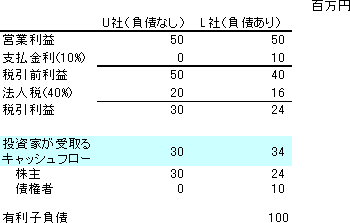
U社とL社の投資家(株主と債権者)が、
受け取るキャッシュフローの額に注目してください。
不思議なことに、
有利子負債があるL社の方が4百万円多いのです。
この4百万円は、一体どこから、きたのでしょうか?
お金が何もないところから、
うみだされるはずがありません。
そうです。実は、法人税の支払額が4百万円減っているんです。
有利子負債があることによって、
利害関係者(ここでは、株主と債権者と国家)間での配分が
変わったということです。
言いかえれば、この4百万円は、
両社の法人税の支払額の差額であり、
L社の支払金利10百万円が、
法人税の課税対象額から控除されていることから
生じているわけです。
この負債の働きを、
負債の節税効果(tax shield)といいます。
この節税効果のおかげで、
最終的に投資家の手にわたるキャッシュフローが、
多くなるわけです。
このキャッシュフローの違いは当然のことながら、
U社とL社の企業価値の違いにつながります。
仮に、U社とL社の営業利益と資本構成が、
このまま永久に一定だとします。
負債があるL社の企業価値を
![]() とし、
とし、
負債がないU社の企業価値を
![]() とすれば、
とすれば、
次の式が成り立ちます。
|
|
つまり、有利子負債があると、
節税効果の現在価値分だけ、
企業価値が高まるというわけです。
この節税効果の現在価値について、
みてみましょう。
支払利息は、
有利子負債の額
![]() に、
に、
負債コスト
![]() をかけた
をかけた
![]() になります。
になります。
負債により、課税対象額は、
この支払利息
![]() だけ少なくなります。
だけ少なくなります。
したがって、
この支払利息に、
法人税率
![]() をかけた
をかけた
![]() が、
が、
節税効果になるわけです。
先ほどの例でいえば、
法人税率40% × 負債額1億円 × 金利10% = 4百円
が節税効果というわけです。
負債があるL社は、今後も永久に、
この節税効果分
![]() というキャッシュフローが、
というキャッシュフローが、
毎期余分に生まれるということです。
このキャッシュフローは、
リスクがない(=永久に一定)と仮定しています。
したがって、この節税効果の現在価値は、
![]()
と計算できるのです。
ちなみに、このとき、
永久債の現在価値を求める公式を使っています。
毎年のキャッシュフローをC、割引率をrとすると、
毎年永久にCを受け取れる永久債の現在価値
![]() は、
は、
![]()
でしたね。
こうして、「負債を利用すると、
節税効果の現在価値分だけ企業価値が高まる」
という、さきほどの関係式が導き出されるのです。
|
|
このことを具体的に考えてみましょう。
ここからは、マニア向けのお話しです(笑)
負債なしのU社の株主資本コスト
![]() を20%とすると、
を20%とすると、
U社の企業価値
![]() は、
は、
次のように計算できます。
|
|
百万円 |
それでは、負債ありのL社の企業価値
![]() は、
は、
どうでしょう。
さきほどの関係式を使えば、
![]() = 150百万円 + 40% × 100百万円 = 190百万円
= 150百万円 + 40% × 100百万円 = 190百万円
となります。
有利子負債があるL社の企業価値が、
U社の企業価値よりも高いというのは、
若干違和感があるかも知れませんね。
L社の
![]() (負債)は、100百万円ですから、
(負債)は、100百万円ですから、
![]() (株主資本)は、90百万円となります。
(株主資本)は、90百万円となります。
それでは、
L社の株主資本コスト
![]() を求めてみましょう。
を求めてみましょう。
株主に帰属するキャッシュフローは24百万円です。
株主資本コスト
![]() とすれば、
とすれば、
|
|
|
| したがって、 |
|
%といえます。 |
負債がないU社の株主資本コスト
![]() は20%でした。
は20%でした。
ところが、負債がある場合の株主資本コスト
![]() は、
は、
26.68%と増加しています。
これは、どういうことなのでしょう?
負債がない場合、株主の直面するリスクは、
事業リスクのみです。
事業リスクとは、
企業の将来生み出すFCFのバラツキと
考えていいでしょう。
これに負債が加わる(=レバレッジをかける)ことにより、
FCFのバラツキが増すことになります。
簡単に言ってしまえば、いいときは、すごくよくて、
悪いときは、すごく悪いことになってしまいます。
レバレッジをかけることによって、
増すリスクを、財務リスクといいます。
このように、負債が加わると、
株主は、事業リスクに加えて、
財務リスクを負担することになるわけです。
したがって、株主のリスク認識が高まるとともに、
経営者に対する期待収益率
(=経営者にとっての株主資本コスト)が、
20%から26.68%に高まったわけです。
ここで、L社のWACCを計算してみましょう。
WACC=株式比率×株主資本コスト+負債比率×(1-40%)×負債コスト
![]()
このWACCを使って、
L社の企業価値
![]() を求めてみましょう。
を求めてみましょう。
投資家である株主と債権者に
帰属するフリーキャッシュフローは30百万円です。
これが永久に続くとすれば、L社の企業価値
![]() は、
は、
次のようにも求められるわけです。
|
|
百万円 |
レバレッジをかけることによって、
株主資本コストは上昇しました。
しかし、
負債コストの比率が上昇したことによって、
結果的にWACCは減少し、
企業価値が増加したことがわかります。
今回のポイントは、
「負債を負債を利用すると、
節税効果の現在価値分だけ企業価値が高まる。」
このことを、法人税率
![]() と負債額
と負債額
![]() が、
が、
永久に一定と仮定することで示しました。
ここで、こんなことをいう人が出てきそうです。
「これって、企業は借り入れをすればするほど、
節税効果分だけ、企業価値を高めることができるってこと?」
まさに、その通りです。
しかし、
できるだけ借入を増やしていこうなんていう企業は、
まずありません。
それは、なぜなのでしょうか?
次回のエッセイでは、
この点について考えてみたいと思います。
【参考エッセイ】
・ Deep KISS第54号「最適D/E比率」
・ BTB第6回「有利子負債の増減(再び)」
2007年2月6日 石野 雄一
ご意見ご感想、お待ちしています。
次回パートナーエッセイは、2月8日(木)に、Yoshihara氏が担当します。