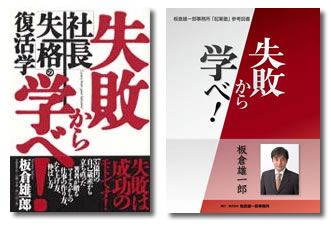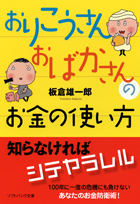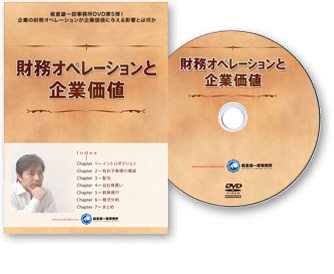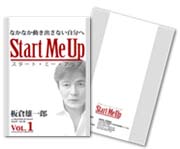2005年6月3日(金曜日)の日本経済新聞の一面中央に、「日本株の割高感修正」という見出しで、日本企業の時価総額が、PER(=Price Earning Ratio=株価収益率=株価/EPS、EPS=Earning Par Share=一株あたり利益)で見た場合、割安になったと言う記事が載っていました。
ふーん(笑)って感じです。
もっと正直に書けば、有利子負債のレバレッジを無視した指標であるところのPERで企業を比較すること自体、この記事書いた人は企業価値について、あまりお分かりで無いようです。
たとえば、高い資本レバレッジの企業の場合、企業価値に占める株主価値(=時価総額を担保する根源)の割合は、レバレッジの分、小さくなります。
しかし、PERの計算式(上記)は、単純に株価を一株あたり利益で割っただけなので、意味無いのです。
そもそも、PERと、時価企業価値(=時価総額+純有利子負債、純有利子負債=有利子負債―現金および現金同等物)には、(少なくとも長期では)ほとんど相関関係がありません。
一方、企業が生み出すネットキャッシュフロー(=純現金収支=投資家から見た企業価値を担保する根源)と時価企業価値(=あくまでも時価総額+純有利子負債)には、強い相関があります。
よって、PERで割高、割安を語ること自体、ほとんど意味がありません。
ですが、僕が、「ふーん」と思うのは、そんな当たり前のコンコンチキレベルの感想ではありません。
KISS第25号「日本企業の価値」で、くどくどと書いたことですが、それを簡単にまとめれば・・・
日本企業を、「現経営者の経営手腕で生み出すことの出来る将来キャッシュフロー」から評価すれば、確かに「割高」の傾向を否定できません。(もちろん、個々の企業は、すべて例外といえます)
しかしながら、日本企業が潜在的に保有している内在価値は、「経営手腕によっては、今予想されるキャッシュフローより、相当に大きなキャッシュフローを生み出す」と評価できます。
この視点で見た場合、日本企業の投資家から見た時価企業価値(=時価総額+純有利子負債)は、「割安」と、少なくとも僕は思います。
(現時点で、現時点の経営陣の経営手腕では、将来キャッシュフローに反映されない内在価値として、具体的には、「特許など知的所有権」、「安過ぎる値段で売られている技術」など、とどのつまりは「優秀な労働力」ということです。)
たとえば、わかりやすい例として(=一方で、異論反論もあるとは思いますが)、ホンダNSXの価格を考えて見ましょう。
ホンダは、NSXを発売開始した当時、スポーツカーの価値の源泉であるところの「Formula One」で、世界最高の実績を誇っていました。もちろん、フェラーリなんて、足元にも及びませんでした。(残念ながら、現在では、フェラーリに一歩譲ります)
それは、乗用車として一般に販売されているホンダNSXと、フェラーリのV8シリーズを、僕自身が実際にサーキットで乗り比べたり、レーシングドライバーの話を聞いたりした限りにおいても、NSXの優位性は、「少なくとも」走行性能においては、高いと言うわけです。
しかしながら、その価格帯が1000万円の中後半にある一般的なフェラーリに比べ、NSXの価格は、1000万円前後と、比較的安いわけです。
「せっかく、F1に多くの、技術的および資本的支出をしたにもかかわらず、もったいない」と、僕は思います。
一般論として、確かに、同じ価値に対して、価格が安い方が、マーケット(この場合、販売市場と言う意味)は、多くを受け入れます。
が、この価格帯の車の価格が、1000万円である場合と、1200万円である場合の販売数に、300万円前後の価格帯の車の場合のような、「大きな差」が生まれるとは思いません。
NSXの話に戻りますが、「いやフェラーリには、エンツォ・フェラーリの歴史があるから特別なのだ!」という意見もあるでしょう。しかし、ホンダにだって、「本田宗一郎」の歴史があるじゃないですか!
日本企業は、既に、「安くて良い商品を提供する企業」ではなく、「高くても、それ以上の価値のある商品を提供する企業」としての道を模索するべきです。
さもなければ、「多少品質に問題があっても、安い商品」を提供できる経済発展途上国の企業と、「文化を背景にした『割高』商品」を提供する欧米企業のハザマにあって、その存在価値が減衰すると思うのです。
日本企業の「技術に根ざしたブランド価値」を高める手腕があれば、「歴史に根ざしたブランド価値」によって儲けを得ている欧米企業より、日本企業は遥かに稼げるはずです。
ワインにだって価値はあります。(僕は大好きです)
しかし、日本酒にだって、世界に誇れる価値があるはずです。
我々日本人の中に、根深くある欧米優位を作り出しているのは、他でもなく我々日本人です。
次のNSXは、フェラーリなど遥かに凌ぐ技術と情熱の塊のはずです。
技術だけではなく、是非、価格も、フェラーリを凌いでもらいたいと思います。
「現経営陣による経営では、今以上のキャッシュを生むことが出来ないと予測するのなら、日本企業は割高といえるのではないか!」という意見もあるでしょう。
確かに、「経営陣も含めて投資の対象とする株式投資」の場合、その通りです。
しかし、現日本企業経営陣の手腕に市場が気を取られ過ぎ、「経営手腕なら任せてくれ」という欧米の投資家によって日本企業が次々に買収されていくようなことがあれば、いつも書いている通り「労働は日本人、経済的付加価値は欧米人のもの」という将来が待っていると危惧します。
たとえば、街に「パン屋」があったとします。
A店は、東京に本社のある企業のフランチャイジー。
B店は、地域住民の出資による独立企業。
そして、仮に「味」に大差が無かったら、この街の住人であるあなたは、どちらの店からパンを買いますか?
もし、住民の多くが、「A店のほうが有名だしブランド好きだし」という理由で、A店ばかりからパンを買っていたら、B店は、いずれ店終いとなります。
結果、B店に出資した地域住民は、「ブランドとの引き換え」に、経済的損失をこうむります。
さらに、「パン屋で働く対価としての賃金」だけを、住民の一部が得るだけで、パン屋が生み出す「経済的付加価値」は、東京の本社に移転することになります。
地域経済は、崩壊します。
あなたは、どっちの方がいいですか?
日本企業の時価企業価値を押し下げている要因は、現経営陣の経営手腕以外にもたくさんあります。
たとえば、企業が生み出す経済価値以上に稼ごうと、社会に対する価値破壊の原因になっていることも知らずに短期トレードに勤しむ「投機家」。
(彼らの異常なまでの期待収益率は、企業の資本コストを押し上げ、企業価値を破壊します。)
たとえば、日本人の金融資産の大部分が、もはや「金融機関」として機能していない銀行などの預貯金となっていること。
(成熟期以降の企業の生み出すキャッシュを、成長期の企業に配分するのが、本来の金融機関の仕事です。)
そして、以上のことが理解できる教育を施してこなかった国家。
国力とは、人口の多少ではありません、「教育の質」如何です。
少子高齢化におびえる前に、その現実を受け入れ、「一人当たりの価値の増大」に取り組むべきです。
話し変わりますが、テーマは同じです・・・
「救急車の有料化」が検討されているそうです。
原因は、「指輪が外れない」という程度の呼び出しによって、救急車の稼働率が上昇し、「本当に救命が必要な患者」に、効率よく救急車が配車されないことなどが原因だそうです。
呆れてしまいます。
一時的な対策としての「有料化」なら、話はわかります。
しかし、根本的な問題は、「指輪が外れない程度で、救急車を呼ぶ」などという、全うな感覚を持っていない馬鹿者が多いということでしょう。
制度では、一時的な解決しかえられません。
そもそも、「制度」によって、問題を封じ込めても、その分、他のカタチで問題が噴出するだけです。
たとえば、「闇金」を規制すれば、「振り込め詐欺」が横行するじゃないですか。
「元から絶たなきゃダメ」なのです。
すべては、教育に依存します。
自分の子供を、東京大学に入れることが「夢」などという、あきれた馬鹿親も問題ですが、そんな馬鹿親を作り出してしまった過去の教育を一掃しなければ、この国に豊かさはやってこないでしょう。
学力より、その学力を持つ「全うな人間性」を作らなければ、お話しになりません。
資格をいくら取得したところで、その資格を有する人間の人間性に問題があれば、社会に対する価値破壊でしかないのです。
馬鹿者が、公認会計士になるから、エンロン事件が起こるのです。
(公認会計士のすべてや、東京大学卒のすべてが馬鹿者だといっているわけではありませんからね)
自分の行為が、社会に対してどのような影響があるかを、考えることが出来る人間を育てることを「教育」と言うのです。
2005年6月6日 板倉雄一郎
PS:
このところ、上記のように「公認会計士のすべてや、東京大学卒のすべてが馬鹿者だといっているわけではありませんからね」などと、くどくど説明しなければならないのは、なぜなのか?と、思うことが多いです。
日本人の文章読解力が低下していることを、僕はひしひしと感じる今日この頃です(笑)
意味わかってくださいね。