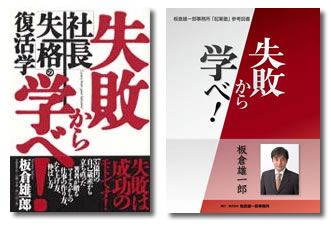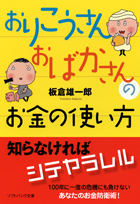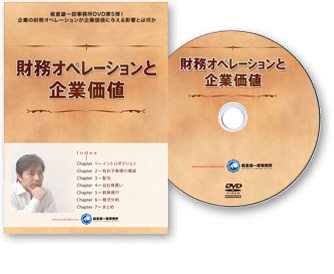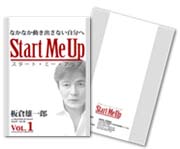今日のエッセイは、経済価値評価理論の基礎について、大サービスです!(あんまり書きすぎると、その内容が企業価値評価セミナーとトレードオフとなりますので、大幅に割愛して書くことにします)
でも、ちょいと難しいですよ。
金融商品の価値算定の方法は、一つしかありません。
それは、何度も書いていることですが・・・
「その商品が生み出す将来フリーキャッシュフローの割引現在価値の総和」です。
これは、「不動産」でも「債券」でも「株式」でも何でもかんでもそうなのです。
「将来フリーキャッシュロー」と聞くと、「キャッシュフロー」という言葉でつまづく方が多いのですが、何てことはない「現金収支」という意味です。
例えば、将来キャッシュフローが事実上確定している債券(たとえば国債)などの価値算定方法について考えてみたい方は・・・
SMU 第64号「企業価値評価シリーズ始動」の中で「債券価格と利回り」について、詳しく書いてあります。
また、不動産の価値算定方法について考えてみたい方は・・・
SMU 第117号「セミナーでの例題」の中で、例題が書かれています。
是非一度、解答にチャレンジしてみてください。
ハッキリ申しておきますが、これが解けないようでは、不動産投資も債券投資も株式投資も間違いなく「博打の域」を出ませんからね。
いずれの例題も、馬鹿馬鹿しいぐらい基礎の基礎です。
当事務所主催「実践・企業価値シリーズ」セミナーでは、最初の一コマ目で、これらの問題を完全に解決できます。
話し戻ります・・・。
将来の現金収支を、いかに正確に予測することができたとしても、その割引率如何によって、割引現在価値は、いかようにも変化します。
たとえば・・・
一年後の110万円を、年率「10%」で現在価値に割り引けば、100万円です。
(100万円を年率10%で運用した場合、一年後に110万円になることの逆と言うわけです)
また、二年後の121万円を、年率「10%」で現在価値に割り引けば、やはり100万円です。
しかし、一年後の110万円を、年率「20%」で現在価値に割り引くと、91万6,000円ほどに低下します。
また、二年後の、121万円を、年率「20%」で現在価値に割り引くと、84万円までその価値が低下します。
つまり、「経済価値=将来キャッシュフローの割引現在価値」を把握する場合、その割引率は極めて重要と言うわけです。
さて、ここで割引率とは、一体何のことだ?と言うことになりますが、概念としては極めて単純で以下の通りです。
(将来キャッシュフローの)割引率
=(投資家からみた)リスク認識
=(投資家からみた)期待収益率
=(資金の受け手からみた)資本コスト
但し、利率固定の債券の場合、資金の受け手から見た資本コストは、表面利率で固定され一定ですが、株式の場合には、上記の様になります。デット・ファイナンスと、イクイティー・ファイナンスの最も大きな違いです。
つまり、予想される将来キャッシュフローが一定の場合、投資家の期待収益率(リスク認識)が高まれば、割引率が上昇し現在価値は低下します。
よって、株式に例えると、当該企業への投資家の期待収益率が高まれば、当該企業の割引現在価値は低下し、多くの投資家は今より低い株価でなければ、投資したくない。となるわけです。
結果、株価は下落し、企業価値は破壊されます。
それでは、投資家の期待収益率とは、一体何か?と言うことになりますが・・・まずそのベースに、「リスクフリーレート」と呼ばれるものがあります。
わかりやすく書けば・・・
「どんなものに投資しても、最低この程度は利回りがあるはず」ということを指し、一般的に「長期国債の利回り(2%程度)」を持ってそれとします。(国債がリスクフリーかどうかの議論は割愛します)
次に、上場株への投資の場合、マーケット全体の「マーケットリスクプレミアム」があります。
これまた、わかりやすく書けば・・・
「上場株に投資するなら、平均してこの程度の利回りがあるはず」
ということを指し、一般的には(頭の良い人たちがTOPIXの価格変動統計から計算した値として)5%程度とします。
さらに、個別企業の株価変動リスクを、マーケット全体(TOPIX)の価格変動に対しての相対的な変動幅を示す値として(これまた頭の良い人たちが計算した)β(ベータ)というものを持ち出し、以上をまとめて・・・
株式資本コスト
=リスクフリーレート+マーケットリスクプレミアム×ベータ
とすることになっています(笑・・・なぜ笑いなのかは後述)
β = 1.0 の企業は、TOPIXと同等程の価格変動履歴を持ち、
β > 1.0 の企業は、TOPIXより大きな価格変動履歴を持ち、
β < 1.0 の企業は、TOPIXより小さな価格変動履歴を持つと言うことです。
「株価変動が大きいほど、その投資リスクは高まる」という、馬鹿げた概念がその根底にあると言うわけです。(笑)
以上の、資本コストの推計方法を、
CAPM(Capital Asset Pricing Mode:資本資産評価モデル)
と言う“らしい”です。(笑)
なぜ僕は、ビジネススクールのファイナンスでも教えているCAPMを笑うのか・・・
笑う理由は簡単です。
当該企業に投資するすべての株主の期待収益率を、「十把ひとからげ」で、カウントしようとするという点が一つ目の笑う理由です。
人それぞれ、当該企業に対する期待収益率はまちまちです。
馬鹿馬鹿しいデイトレ情報に毎月何万円も支払っている人も居るし、
(当然、このような人にとって、この情報コストは、期待収益率に上乗せされます)
きちんと企業価値評価をした結果、たった一度だけしか取引しない人も居ます。(例えば、ウォーレン・バフェット氏は、この手法で、世界一の投資家となりました)
それぞれ、期待収益率は違っています。
また、そもそも「リスクフリーレート=長期国債の利回り」とすることに疑問を持つ人も居るでしょう。
「日本国債より、トヨタ自動車の方がリスクフリーだよ」とか。
つまり、当該企業へ投資する人は、個々別々の期待収益率を持っていると言うことです。従って、最も正確で、最も非現実的な株式資本コスト(=投資家の期待収益率)を測定する方法は、当該企業に投資している投資家すべてに期待収益率をヒアリングし、その投資額による加重平均をとると言うことになります。
が、ありえませんよね、そんなこと。(笑)
もう一つのCAPMを笑う理由は・・・
「そもそもファンダメンタル分析であるはずの企業価値評価を行う際、最もインパクトの大きな割引率の計算に価格変動リスクというテクニカルファクターを使っている」という点です。
もうたまりません(笑)
そもそも、株価と言うのは、当該企業の株主の内「たった二人が同じ株価で出会って取引しただけ」でも形成されてしまうのです。
株価は、価格であり、価値ではないのです。
価値算定を行うのに、価格変動リスクを持ち出すようでは、呆れてしまいます。
世の頭の良い方々の間でも、徐々に、「CAPMってどうなのよ?」という議論が始まっています。ですがこれに代わる「客観的なモデルが見つからない」という理由で、消極的にCAPMを用いていると言うのが現状です。
しかし、僕は、こう思うのです。
いかなる投資活動においても、それが投資である以上『客観的な評価』などありえないと。
つまり、投資が自己責任である以上、投資家が自分で価値評価を行い、その上で自分の期待収益率以上のリターンが見込めると判断した場合にのみ、投資を実行するという、当たり前のコンコンチキを、頭の良い人たちは、忘れていると言うわけです。
(というか、他人の金を預かって運用する機関投資家としては、失敗したときのイイワケとして、「客観的(笑)」なCAPMを使うのでしょうけどね)
人の判断に頼って投資するなら、最初から個別企業などへの投資などせずに、投資信託に任せればいいじゃないですか。
プロでも、実はインデックス(たとえばTOPIX)より、その運用実績は低いのですよ。
彼らの運用実績が低い理由は、βに始まるインチキCAPMのイイワケに頼るからに他なりません。(そもそも、βと市場の相関関係が極めて低いことは、それこそ既に証明されています)
と、いろいろ書いてきましたが、僕は現在のCAPMに変わる、newCAPMの手法を持っています。
これは、そのうちどこかで発表しようとは思います。
勿体ぶっているのではなく、この理論の「統計的な立証=現在のCAPMによる価値算定より相関が強いことを示す」がまだ完了していないからです。
どなたか統計学に詳しい方がおいででしたら、お手伝い願います。
当事務所のパートナーは、このnewCAPMの方が、明らかに現実的であることを、僕と同様、直感的に理解してしまっているので(笑)、なかなか数値検証をしてくれないのです(ぶぅ~)。
ご協力願える方は、スタッフ応募してください。よろしくです。
ですが、このnewCAPMですら、「個別企業を精査し、自ら判断する」事に比べれば、とるに足らない手法です。
結果僕が、SMU 第103号「資本コストと割引率」で表現した内容であるところの「自分勝手割引率」による企業価値評価手法以上の手法は、ありません。
2005年3月3日 板倉雄一郎
PS:
以上をもっと詳しく正確に知りたい方がいらっしゃいましたら、是非セミナーに。
以上がチンプンカンプンなら、尚更セミナーに。
僕の声(音)、身振り手振り(動き)、そしてサポート要員による個別サポートを受けるのは、文章を読むより、はるかに学習効果が高いです。
さらに、学習結果をエクセルの数式として持ち帰れます。
これを一旦手に入れれば、企業(株式投資)だけでなく、あらゆる金融商品の価値算定が可能になります。
断言します。