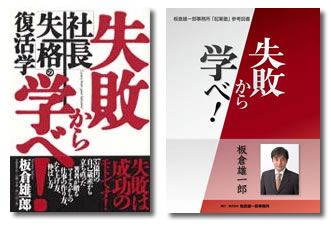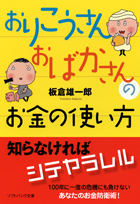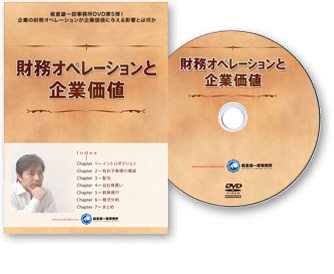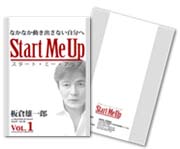本当にしつこいですが、まずはセミナーの話題からです。
昨日(11月28日)をもち、当事務所主催、東京第一グループのセミナー全6回が終了いたしました。受講生の皆さんには、概ね満足いただけたのではないか?と自負しております。
どのグループも最終回は、これまでの学習を基に受講生が宿題として実施した特定企業のバリュエーションと、当事務所パートナーが実施したバリュエーションとを比較します。
この比較、大変面白いです。学習の成果もあって、過去の業績分析については、受講生同士、受講生と当事務所パートナーと受講生の数値にほとんど開きはありません。
将来業績予測となると、それぞれの「予測シナリオ」が、全く異なり、結果、バリュエーション(企業価値、株主価値)に大きな開きが生じます。ですが、これまた学習の効果もあってか、「トンデモナイ違い」にはならず「絶対に無いとは言えないよね」という範囲に収まるわけです。
株式市場での取引とは、現在の株価を「高い」と感じる人と「安い」と感じる人が出会うことで始めて売買が成立するわけですから、この点に関しては、受講生といえども、個人の感覚や予測を否定することはできません。
ですから、あくまで「比較対象」を提供するということにとどめているわけです。だから、面白いのです。世の中いろんな見方があるんだなぁ~と、実感することができます。
変な表現ですが、将来業績予測(とは即ち企業価値そのものです)が、セミナーの学習効果によって、非常に小さな範囲にとどまるとすれば、それはすなわち「セミナーとしては失敗である」と僕は考えています。
もし、皆が同じような結果を得るようになるとすれば、セミナーなど全く必要ありません。アナリストの発表するデータを信じて投資すればよいわけですから。
でも、投資で大成功を収めた方々の多くは、「アナリストレポートには、目を通さない」と断言しているように、クライアントの希望に沿って「丸めた数値」と、自らの職を失わないような結論を頼りにはできません。
ところで、最終回には、これまでの復習を実施するために参考図書である「企業価値評価(Valuation)」(マッキンゼー・アンド・カンパニー)の、必須復習項目ページの一覧をお教えするわけです(もちろん受講生の皆さんは、この本を手元に持っているわけです)が、そのとき受講生の方は、始めて気がつくわけです・・・
「あっ!あの回の話は、ここに載っているじゃないか」とか、
「あれ?板倉の説明は、この部分に書いてあるじゃないか」と。
(断っておきますが、受講生の皆さんが「なぁ~んだ、最初から本で学習できたじゃないか」とクレームを言っているわけではありませんからね。)
確かにそうです。バリュエーションそのものの基本的な手法を僕自身が開発したならともかく、世間一般ではありませんが、アナリストをはじめとするその手のプロの間では、「あたりまえ」のことをまとめた参考図書をベースに、講義を行っているわけですからね。
で、受講生の方々は、次の瞬間気がつくわけです・・・
「最初、全くチンプンカンプンだったこの本の大部分を自分は理解している」と。
DCF(ディスカウント・キャッシュフロー)法の概要は知っていても、それをシートに計算式で落とし込むことはしたことが無かったという方が、講義終了後の懇親会で・・・・
「あの宝くじ(米国の100億円を越えるジャックポッド)の一括払いと、分割払いの差を計算したら、およそ4.5%ぐらいの利回りに相当するから、僕なら一括払いにするなぁ」とか、
「私の推計したWACC(加重平均資本コスト)は、高すぎだったんですよ」とか、
「あの会社の継続価値算定の、g(成長率)は、市場が織り込んでいるほど高くない」とか、
「今日のバリュエーション対象企業は、私の場合、余剰資金もカウントしていたから、ROIC(投下資本利益率)が低くなったんだなぁ」などと、会話が弾むわけです。
すばらしいです。
つまり当事務所が、受講生に提供する最も重要な価値とは、
|
1.バリュエーション学習の「機会提供」 2.不安の解決 3.使えるツールとシートの提供 企業をスクリーニングする「クイック分析シート」から、 |
というわけです。
セミナー終了後は、学習効果を最大化するために、何度も繰り返すことで、個々の企業のバリュエーションを実施し、「計数感覚」を磨くという作業が続きます。
更に得られた結果に基づき、実際に投資活動を行い、時には損失を出し、時には儲け、その繰り返しの中から最終的に、フィナンシャル・リテラシーを身に付け、結果として資産形成を実現できるということになります。
恐らく、受講生同士のコミュニケーションの場として設定したメーリングリストは、長期にわたり彼らの「一人ぼっち不安」を解決することとなるでしょう。受講生の10年後、20年後がとても楽しみです。
そういえば、今日(11月29日)も、スペースキー様主催セミナーの最終回です。こちらもとても楽しみです。
今日のところは、セミナー関係はこの程度で。
さて本題、「企業の資源リスク」についてです。
日産自動車の鋼鈑不足による工場一時休止。
吉野家D&Cの米国産ショート・プレート入手不能による業績悪化。
情勢不安と生産設備余力の減少(および投機)による、原油高などなど、このところ、恐らく多くの人が「リスク」として捉えていなかった資源の調達に関する問題が次々と発生しています。
この傾向は、今後の世界経済を占う上で、最も警戒しなければならないリスクとなりえるでしょう。
中国やインドの爆発的な経済発展が、世界の資源を飲み込んで行くわけですから、今はまだ「無くても死にはしない」という範囲ですが、そのうち我々が生きていくために絶対に必要な「水や食料」にも、その影が・・・。全然大げさな話ではないと、僕は思っています。
少なくとも、企業のバリュエーションを行うとき、当該企業が価値を創造するにあたり必要な資源が何であるか?
その資源は、現在の消費量で、どの程度の期間、安定供給を受けられるのか?
また、その場合のコストは、どのように推移するのか?
については、資本構成以上に重要なリスクファクターとして認識しなければならない時代です。これまでも、「資源銘柄」とはじめから認識されているエネルギー関連企業などは、以上のリスクファクターは、当たり前のように織り込まれていましたが、そうではない企業の場合でも、このあたり精査しなければ、現実に使えるバリュエーションには、なりえないということです。
(有価証券報告書の「リスクファクター」は、僕が最も楽しく読んでいる項目ですが、多くの場合「原材料の価格高騰」については触れられていますが、「原材料の調達不能の可能性」については、あまり目にしたことがありません。)
日本においては、そもそも資源の多くを海外に依存している関係で、ある程度その下地はありますが、今後は、「人」という資源で躓く可能性を否定できません。恐らく全うな教育を受けた人材の不足が深刻になるでしょう。
たとえば、古くは、「コカ・コーラ」。
知っている人は知っている・・・コカ・コーラの「コカ」は、コカの葉の抽出液を原料としていたことから付けられたブランド名です。
「コカの葉の抽出液」とは、すなわち「コカイン」のことです。
(名前を失念しましたが、確かイタリアのリキュールでも、コカインを調合していたブランドがあります。)
当然ながら現在では、コカはブランドの名前だけになっています。
法規制によりコカを調合することはできなくなったことが原因です。ですが、それまで「薬」のように扱われていたこの製品は、この法規制により、資源調達が不可能になったおかげで、それを一般化(ジュース化)することに成功し、現在に至るまですばらしい業績を上げることができたわけです。
鋼鈑が手に入らないなら、アルミニウムで作る、それもコストが高いなら、ポリカーボネートで作る、というのは、ちょっと非現実的ですが、そんなオペレーションができる経営者の経営する企業に投資したいものです。
たとえば、最近では、「吉野家」。
我々の分析ではこの企業、既に市場から見放されているのではないか?
という結論を得ています。現実的には、既にギャンブル株になっているのではないでしょうか?
「顧客は、『吉野家の味』を期待しているんだ。だから米国牛しか使えない」という経営判断があったということですが、実際には「顧客は、単に牛丼を期待していただけ」だったのではないでしょうか?
競合企業との売り上げの差、株価推移、メディアでの報道など、あらゆる場面でこの現象は数値として現れています。
個人的には、「がんばれ吉野家」なのですが・・・
資源のリスクは、今後あらゆる企業の株価を大きく左右する要素になりえますよね。
少なくとも、サプライチェーンの集約(調達企業の整理)が、必ずしも良い結果を生まない可能性はありますよね。
今日は、こんなところで。
2004年11月29日 板倉雄一郎