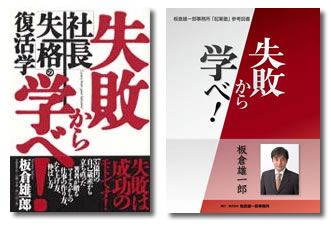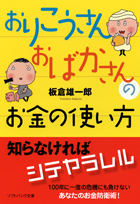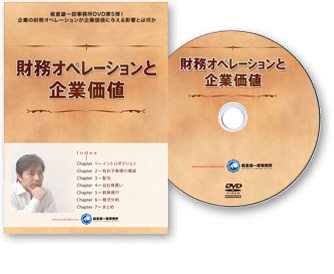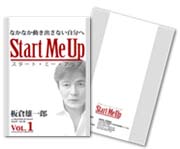6月23日付け日本経済新聞の5面(オピニオン)に、「領空侵犯」というコラムがあります。
「排出量取引の導入”待った”」という見出しで、デフタ・パートナーズの原丈人氏がインタビューに答えています。
(ハイパーネット時代に、原氏が同社への投資を検討する際、一度お会いしたことがあります。)
この記事による彼の主張は概ね・・・
1、排出量取引を導入しても温暖化ガスの排出量は減らない。
2、キャップ&トレードではなく、キャップだけにした方が効果的である。
3、トレードを導入すると、温暖化ガスの削減に取り組むより、安易に排出権を取得しようとする。
4、トレードは、それを投機対象とする向きによって、サブプライム問題の二の舞になる。
5、各国が税制などを生かし再生エネルギーや省エネの技術開発を促進することである。
といった内容です。
僕の意見も原氏と「ほぼ」同じです。
ただし、税制によって、排出ガス削減インセンティブが本当に効果的に働くのか、少々疑問ではあります。
また、昨今の各企業の「排出権付き商品で集客」(←日本経済新聞6月21日付け夕刊1面)といった「マーケティング戦略上の排出権取引の利用」についても、それらの基本は、「消費者の自然保護に対する関心」によってのみ成立するカーボンオフセット行為ですから、「排出権を買うことができても、排出削減に直結するとは限らない」という問題があります。
「排出権」という新たに生まれた経済価値の扱い方について、各国、各企業とも、それなりに「テスト的に」、様々な手法を模索中ということですが、本来、「その仕組みによって、温暖化ガスの排出が減る」ということが本当の目的「のはず」という視点から評価すれば、どれもイマイチといわざるを得ません。
もっとわかりやすくて、もっとインセンティブがあって、もっと効果的なモデルが必要ですね。
2008年6月27日 板倉雄一郎