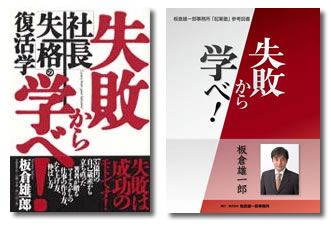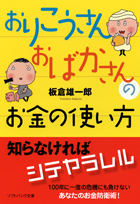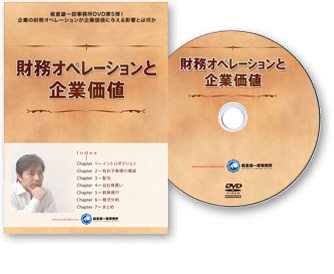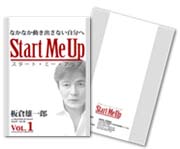(昨日の、パートナーエッセイと内容がダブりますがお付き合いください。)
2007年に入ってから、株式相場は、サブプライム問題に始まる「好ましくないニュース」が出るたびに、ジリジリと下げています。
何を隠そう、僕自身のポートフォリオについても、当然ながら、評価損が膨らんだり、評価益が減少したりするケースの方が多いわけです。
しかし、評価損益「だけ」を見て、慌てて損切りしたり、(上げている時は)喜んで余計なものを買ったり(笑)を繰り返していれば、資産はどんどんなくなってしまいます。
こんなときにも、
「支払う価格以上の価値を手に入れる」という考え方が大切です。
まずは、極めて基本的なことですが、
「Aさんが、1年前に一株1000円で投資した株式が、今日現在1200円だとします。この場合の、Aさんの『今日現在』の投資額は一体いくらでしょうか?」
1000円でしょうか?
それとも、1200円でしょうか?
答えはもちろん、1200円です。
「えっ? だって投資したのは1年前の1000円じゃないの?」
と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、今日現在、Aさんは、市場価格の1200円で株式を売却することができるにも関わらず、その機会を利用せず、引き続き保有し続けるわけですから、
「一旦1200円で利益確定し、直後に1200円で同じ株式に投資すること」
と、
「そのまま保有すること」
は、(売買手数料や税を除けば)、ほとんど同じことを意味します。
よって、
上記Aさんの今日現在の投資額は、
「その時点での評価損益がどうであれ」、
今日現在の株価*株式数ということになります。
以上の考えに基づけば、合理的な利益確定の基準をつくることができます。
多くの個人投資家の利益確定は、
「その時点での評価損益」によって判断する傾向があります。
しかし、以上の考えに基づけば、
「その時点での評価損益」より、評価損益がどうであれ、
「今日の株価で投資をするかどうか」を、
一株あたりの「価値」と「株価」を比較して判断することが合理的だといえます。
「今日の株価では、その価値に対して相当に割高だ」と判断すれば、
(評価損益がどうであれ)利益確定の良い機会になりえますし、
「今日の株価では、その価値に対して相当に割安だ」と判断すれば、
(評価損益がどうであれ)引き続き保有を続ける合理的理由になります。
つまり、
「支払う株価以上の価値を手に入れる」
という考えは、投資実行時点だけではなく、反対売買(=利益確定)の場合にも用いるべきだということです。
もちろん、
「買い」による投資に対する利益確定は、「売り」ですから、この場合、
「差し出す価値以上の価格を手に入れる」
という条件になります。
そもそも、「評価損益」とはなんでしょうか?
儲けや損を示す数値でしょうか?
違いますよね。
確かに、その時点で反対売買をするなら、評価損益が実損益になるわけですから、儲けや損を表すことになります。
しかし、反対売買をする前であれば、評価損益とは・・・
「過去に自分が投資した株価と、現在の市場株価の差」
でしかないわけです。
評価損益に翻弄されるということは、投資時点でどれほど価値算定を行ったとしても、「価格変動(ミスターマーケット)に翻弄される投資」に他ならないわけです。
以上のような合理的な売買機会判断を行うためには、当然ながら「価値算定」が必要になります。
特に、「保有し続けるかどうか」を判断するためには、現時点での情報に基づき、再度企業価値評価を行う必要があるわけです。
サブプライム問題に起因する「為替変動」や「米国経済の行方」は、当然ながら、「株価」だけではなく、「一株あたりの価値」にも影響をもたらします。
たとえ内需関連株であったとしても、(その具体的な影響を計るのは極めて難しいですが)回りまわって為替や米国経済の影響を受けます。
これらの「変化」を、企業価値評価に折込み、
その上で、株価と一株あたり価値を比較し、
「割安でしかも時間経過と共に価値が増大するであろう」
と判断するのであれば、
(評価損益がどうであれ)保有を継続すべきですし、
「割高でしかも時間経過と共に価値が増大するとは限らない」
と判断するのであれば、
(評価損益がどうであれ)反対売買(=利益確定)をするべきだと思います。
さて、皆様のポートフォリオは、いかがでしょうか?
これだけ下げ相場が続いても、
「その企業、欲しいが、まだまだ割高で手が出せない」
という企業、結構あります。
つまり、
下げ相場の時ほど、投資家から観て「いい企業」に、資金が集中するわけです。
逆に言えば、「いい企業」ほど、「下げ相場に強い」と言えます。
もろもろ書いてきましたが、要するに、
投資を実行する場合も、
投資を解消(反対売買=利益確定)する場合も、
「価値と価格の比較」による売買判断が必要ということです。
評価損益にビビる時間があったら、その時間を使って冷静に企業価値評価を行い、一株あたりの「現時点での」妥当な株価を再度算出した上で、売買判断を行うほうが、価格変動に翻弄されるより、遥かに合理的です。
2007年9月12日 板倉雄一郎
2007年09月12日
ITAKURASTYLE「売買機会の判断」
- Previous Entry:
- IR物語 第19回(番外編)「ミスターマーケットとの付き合い方」
- Next Entry:
- 経営経験者からみた投資 第6回「失敗から得られるもの」
エッセイカテゴリ
ITAKURASTYLEインデックス
- ITAKURASTYLE 連載に関するお知らせ
- ITAKURASTYLE「順張りの功罪」
- ITAKURASTYLE「オープンセミナーランナップ」
- ITAKURASTYLE「借金が無ければ金利上昇のダメージを受けない?!」
- ITAKURASTYLE「キャップ&トレードは効果的?!」
- ITAKURASTYLE「内部抵抗」
- ITAKURASTYLE「エコ替え」
- ITAKURASTYLE「ベンチャー精神」
- ITAKURASTYLE「TOYOTA iQ」
- ITAKURASTYLE「デリバティブの正しい使い方」
- ITAKURASTYLE「一言エッセイ『幸福論』」
- ITAKURASTYLE「ニュースアップデート~金融工学の罠」
- ITAKURASTYLE「週末の徒然」
- ITAKURASTYLE「食糧(価格)危機~アメリカのビジネスモデル」
- ITAKURASTYLE「日本企業の資本効率」
- ITAKURASTYLE「アービトラージ(裁定取引)」
- ITAKURASTYLE「悲観的に見える楽観論」
- ITAKURASTYLE「経済動向と相場の見通し」
- ITAKURASTYLE「ニュースアップデート」
- ITAKURASTYLE「虚業と実業」
- ITAKURASTYLE「最後の合宿セミナーランナップ」
- ITAKURASTYLE「自分を信じることによる一貫性」
- ITAKURASTYLE「あなたの顧客は上司じゃない」
- ITAKURASTYLE「リハビリウィーク」
- ITAKURASTYLE「インプットモード」
- ITAKURASTYLE「プロセスにこそ価値の源泉がある」
- ITAKURASTYLE「スーパーマン経営者の問題」
- ITAKURASTYLE「過去は追いかけてくる」
- ITAKURASTYLE「上場おめでとう!」
- ITAKURASTYLE「本末転倒」
- ITAKURASTYLE「金庫株の取り扱い」
- ITAKURASTYLE「タクシードライバー症候群など」
- ITAKURASTYLE「カマナブカ精神」
- ITAKURASTYLE「ドル安」
- ITAKURASTYLE「カーボンダイエットシステムの提案」
- ITAKURASTYLE「わがまま息子の甘やかし」
- ITAKURASTYLE「第29回合宿セミナーランナップ」
- ITAKURASTYLE「不祥事を探せ」
- ITAKURASTYLE「温暖化ガス排出権取引」
- ITAKURASTYLE「外資規制」
- ITAKURASTYLE「日本経済新聞より」
- ITAKURASTYLE「自分で調べ、自分で考える」
- ITAKURASTYLE「渋滞を作っているのは自分自身」
- ITAKURASTYLE「バフェット氏の提案と株価」
- ITAKURASTYLE「ポスト(アメリカ流)資本主義」
- ITAKURASTYLE「MS vs Google」
- ITAKURASTYLE「バフェット&ゲイツ」
- ITAKURASTYLE「ニュース盛りだくさん」
- ITAKURASTYLE「Microsoft TOB Yahoo!」
- ITAKURASTYLE「日本人が買えばイインダヨ!」
- ITAKURASTYLE「世界は一つ」
- ITAKURASTYLE「まだはもうなり、もうはまだなり。」
- ITAKURASTYLE「月極さん(笑)」
- ITAKURASTYLE「ハーレム」
- ITAKURASTYLE「シュリンクにっぽんに喝!」
- ITAKURASTYLE「投資タイミング」
- ITAKURASTYLE「セミナーランナップ」
- ITAKURASTYLE「リクエストに答えて」
- ITAKURASTYLE「低炭素経済」
- ITAKURASTYLE「下げ相場は絶好の投資機会?」
- ITAKURASTYLE「クリパ2007ランナップ」
- ITAKURASTYLE「自己投資」
- ITAKURASTYLE「食べ物を考えよう」
- ITAKURASTYLE「朝」
- ITAKURASTYLE「あれから10年」
- ITAKURASTYLE「恋しい仕事」
- ITAKURASTYLE「金融の一人歩き、なら結構だが」
- ITAKURASTYLE「個別企業再評価のススメ」
- ITAKURASTYLE「経済的危機の意味」
- ITAKURASTYLE「訂正とリロードのお願い」
- ITAKURASTYLE「やっぱり個別企業の評価が大切」
- ITAKURASTYLE「赤福モード」
- ITAKURASTYLE「米国経済について」
- ITAKURASTYLE「経済・金融関連の書籍を読んで」
- ITAKURASTYLE「己を知る」
- ITAKURASTYLE「短期と長期(積み上げるとずれてくる)」
- ITAKURASTYLE「リクエストに答えて?PIPEs」
- ITAKURASTYLE「久々の第三春美」
- ITAKURASTYLE「リスクを知りたがる人、知りたくない人」
- ITAKURASTYLE「セミナーランナップ&お知らせ」
- ITAKURASTYLE「リクエストに答えて(3)サブプライムローン問題その2」
- ITAKURASTYLE「経済指標は信頼できる?」
- ITAKURASTYLE「リクエストに答えて(2)サブプライムローン問題」
- ITAKURASTYLE「リクエストに答えて(1)新興国への投資」
- ITAKURASTYLE「書いて欲しいこと募集中!」
- ITAKURASTYLE「週末の徒然(とお知らせ)」
- ITAKURASTYLE「インフレに強い企業」
- ITAKURASTYLE「週末の徒然(円天など(笑))」
- ITAKURASTYLE「久々のお呼ばれ講演」
- ITAKURASTYLE「利息制限法の弊害」
- ITAKURASTYLE「NICE TRY!」
- ITAKURASTYLE「割高スクリーニングのススメなど」
- ITAKURASTYLE「大阪セミナーランナップ」
- ITAKURASTYLE「釣られているのは誰?」
- ITAKURASTYLE「安倍首相突然の辞任」
- ITAKURASTYLE「売買機会の判断」
- ITAKURASTYLE「継続は力なり」
- ITAKURASTYLE「お金の話(&週末のお知らせ)」
- ITAKURASTYLE「夏休みランナップ」
- ITAKURASTYLE「必要条件≠十分条件」
- ITAKURASTYLE「週中の徒然(所有幻想など)」
- ITAKURASTYLE「自民惨敗」
- ITAKURASTYLE「セミナーランナップ」
- ITAKURASTYLE「読者の皆様に感謝、と注意事項」
- ITAKURASTYLE「水」
- ITAKURASTYLE「週末の徒然(マイブーム)」
- ITAKURASTYLE「村上氏に実刑判決」
- ITAKURASTYLE「バリューズ・ブート・キャンプ」
- ITAKURASTYLE「ブルドックのストップ安に関する解説」
- ITAKURASTYLE「高裁決定の要旨について」
- ITAKURASTYLE「つまるところ」
- ITAKURASTYLE「ブル社の買収防衛策に対する高裁判断の影響」
- ITAKURASTYLE「ブルドックの株価推移(笑)」
- ITAKURASTYLE「高裁、ブル社買収防衛策を容認」
- ITAKURASTYLE「全く新しいビジネスモデル(改)」
- ITAKURASTYLE「インカムゲインとキャピタルゲイン」
- ITAKURASTYLE「スティール vs ブルドック(の経営陣)」
- ITAKURASTYLE「インフレと為替と金利」
- ITAKURASTYLE「株主総会レポート(ブルドックなど)」
- ITAKURASTYLE「週末の徒然」
- ITAKURASTYLE「マーケット考察」
- ITAKURASTYLE「投資循環~日産とゴーン経営」
- ITAKURASTYLE「スティールパートナーズ(3)」
- ITAKURASTYLE「経営者なのか錬金術師なのか」
- ITAKURASTYLE「スティールパートナーズ(2)」
- ITAKURASTYLE「スティールパートナーズ(1)」
- ITAKURASTYLE「DCF法は最悪だ!」
- ITAKURASTYLE「ホットストック:DI社自己株取得を発表」
- ITAKURASTYLE「DI社株主総会」
- ITAKURASTYLE「雄太ありがとう」
- ITAKURASTYLE「コストコ ホールセール」
- ITAKURASTYLE「オリエンテーリングの想い出」
- ITAKURASTYLE「株主総会で何を見るべきか」
- ITAKURASTYLE「キャンプ生活一ヶ月経過」
- ITAKURASTYLE「キャンプ生活26日目」
- ITAKURASTYLE「オープンセミナーランナップ」
- ITAKURASTYLE「価値観の多様性?」
- ITAKURASTYLE「堀会長からの回答」
- ITAKURASTYLE「堀会長への手紙」
- ITAKURASTYLE「リーフカレント」
- ITAKURASTYLE「週中の徒然」
- ITAKURASTYLE「独り言(笑)」
- ITAKURASTYLE「真っ当な株式投資を書いた理由④」
- ITAKURASTYLE「電子マネーに関する頭の体操」
- ITAKURASTYLE「真っ当な株式投資を書いた理由③」
- ITAKURASTYLE「真っ当な株式投資を書いた理由②」
- ITAKURASTYLE「制度改革では改革はできない」
- ITAKURASTYLE「ホリエモンに実刑判決」
- ITAKURASTYLE「確定申告」
- ITAKURASTYLE「合宿セミナーランナップ」
- ITAKURASTYLE「株安の連鎖」
- ITAKURASTYLE「実感の信頼性」
- ITAKURASTYLE「思い込み」
- ITAKURASTYLE「ミスターマーケットは気前がいい!」
- ITAKURASTYLE「バーゲンセール?」
- ITAKURASTYLE「日興コーディアル」
- ITAKURASTYLE「週末の徒然」
- ITAKURASTYLE「真似をすることは不幸の始まり」
- ITAKURASTYLE「ごめんなさい」
- ITAKURASTYLE「第23回合宿セミナーランナップ」
- ITAKURASTYLE「言葉狩り」
- ITAKURASTYLE「女性は産む機械」
- ITAKURASTYLE「亀戸餃子」
- ITAKURASTYLE「格差問題」
- ITAKURASTYLE「超・格差社会アメリカの真実」
- ITAKURASTYLE「欲しいなら」
- ITAKURASTYLE「富の独裁者」
- ITAKURASTYLE「政府財政悪化の本質」
- ITAKURASTYLE「納税義務」
- ITAKURASTYLE「Google」
- ITAKURASTYLE「休日の徒然」
- ITAKURASTYLE「第22回合宿セミナーランナップ」
- ITAKURASTYLE「指導者の条件」
- ITAKURASTYLE「ルックスルーで考える団塊世代の退職」
- ITAKURASTYLE「2007年明けましておめでとうございます」
- ITAKURASTYLE「X'mas & My Birthday」
- ITAKURASTYLE「クリスマスの独り言」
- ITAKURASTYLE「クリパの情景」
- ITAKURASTYLE「クリパ2006」
- ITAKURASTYLE「ワーキングプア」
- ITAKURASTYLE「歳を重ねると」
- ITAKURASTYLE「もろもろ」
- ITAKURASTYLE「クレージーな集団」
- ITAKURASTYLE「ルックスルーで考える」
- ITAKURASTYLE「チャンスに取り組む姿勢」
- ITAKURASTYLE「欲」
- ITAKURASTYLE「経済は循環する」
- ITAKURASTYLE「経営なのか、博打なのか、社会活動なのか」
- ITAKURASTYLE「知識、常識、価値観」
- ITAKURASTYLE「ワークアウト」
- ITAKURASTYLE「年率30%」
- ITAKURASTYLE「人」
- ITAKURASTYLE「経営と錬金術」
- ITAKURASTYLE「合宿セミナーランナップ」
- ITAKURASTYLE「通話料ゼロ円」
- ITAKURASTYLE「読者からの意見」
- ITAKURASTYLE「多すぎる私たち」
- ITAKURASTYLE「若さは価値」
- ITAKURASTYLE「ナンバーポータビリティー」
- ITAKURASTYLE「第三春美」
- ITAKURASTYLE「法人税の負担者」
- ITAKURASTYLE「セールス・プレゼンテーション」
- ITAKURASTYLE「意思決定」
- ITAKURASTYLE「それで、どのくらい儲かるの?」
- ITAKURASTYLE「第一回ビジネスプレゼン大会ランナップ」
- ITAKURASTYLE「権威の怖さ」
- ITAKURASTYLE「ルックスルー」
- ITAKURASTYLE「ソフトバンク、携帯事業を証券化(続編)」
- ITAKURASTYLE「ソフトバンク、携帯事業を証券化」
- ITAKURASTYLE「知識を伝える理由」
- ITAKURASTYLE「事業提案とファイナンス」
- ITAKURASTYLE「オジサン」
- ITAKURASTYLE「期待と期待収益率(再び)」
- ITAKURASTYLE「リスク&リターン」
- ITAKURASTYLE「ミクシィ上場~初値付かず!」
- ITAKURASTYLE「Back to Basic」
- ITAKURASTYLE「ああ株価対策」
- ITAKURASTYLE「9.11」
- ITAKURASTYLE「再チャレンジ可能な社会の実現」
- ITAKURASTYLE「GMOって、忙しいですねぇ」
- ITAKURASTYLE「リアリティーの欠如」
- ITAKURASTYLE「ご祝儀相場」
- ITAKURASTYLE「紀子さま、男の子ご出産」
- ITAKURASTYLE「価値評価と信用格付け」
- ITAKURASTYLE「企業買収」
- ITAKURASTYLE「再び、ミクシィ上場・・・その盲点」
- ITAKURASTYLE「ミクシィ上場」
- ITAKURASTYLE「王子、北越TOBを断念」
- ITAKURASTYLE「ネット企業世代交代の波」
- ITAKURASTYLE「雇用形態」
- ITAKURASTYLE「資本コストは支払い金利だけじゃないのよ」
- ITAKURASTYLE「箱より計画」
- ITAKURASTYLE「うれしい たのしい」
- ITAKURASTYLE「敵対的M&A 生き残りのためのM&A」
- ITAKURASTYLE「知識とリスクヘッジ」
- ITAKURASTYLE「自業自得」
- ITAKURASTYLE「サンデープロジェクト2006/07/16」
- ITAKURASTYLE「潮時」
- ITAKURASTYLE「おりこうさんとおばかさん」
- ITAKURASTYLE「ゼロ金利解除」
- ITAKURASTYLE「私はそんなに馬鹿じゃないもん!」
- ITAKURASTYLE「ゲーム理論」
- ITAKURASTYLE「知識レバレッジ(SF)」
- ITAKURASTYLE「オマケ」
- ITAKURASTYLE「日銀福井総裁の資産」
- ITAKURASTYLE「結果より過程」
- ITAKURASTYLE「バフェット氏の寄付」
- ITAKURASTYLE「理念か、計画か」
- ITAKURASTYLE「至福のリストランテ」
- ITAKURASTYLE「国会茶番劇」
- ITAKURASTYLE「大切なのはディフェンスなんだよ!」
- ITAKURASTYLE「読者からのメール」
- ITAKURASTYLE「セミナーランナップ」
- ITAKURASTYLE「New LEGACY Press Conference」
- ITAKURASTYLE「村上会見」
- ITAKURASTYLE「Fly me to the moon.」
- ITAKURASTYLE「Wonderful Tonight」
- ITAKURASTYLE「リアルバリュ会ランナップ」
- ITAKURASTYLE「ワークアウト」
- ITAKURASTYLE「近況」
- ITAKURASTYLE「なんでそーなるの!」
- ITAKURASTYLE「お金を大切に扱う」
- ITAKURASTYLE「粋な話(BA)」
- ITAKURASTYLE「もし僕が・・・」
- ITAKURASTYLE「もっともっと」
- ITAKURASTYLE「ファイナンスを学ぶということ」
- ITAKURASTYLE「GW&セミナーランナップなど」
- ITAKURASTYLE「おーい!日本経済新聞さんよぉー!」
- ITAKURASTYLE「メディアの方々へ」
- ITAKURASTYLE「ゴールデンウィーク!」
- ITAKURASTYLE「セミナーランナップ~楽しむということ」
- ITAKURASTYLE「ばら撒くなら金より知識」
- ITAKURASTYLE「懲りたくん#1」
- ITAKURASTYLE「思いやりのサンタクロース」
- ITAKURASTYLE「どうして伝わらないのか?」
- ITAKURASTYLE「どうするニッポン!を観て」
- ITAKURASTYLE「メッセージ」
- ITAKURASTYLE「リフレッシュ!」
- ITAKURASTYLE「セミナーランナップ~特別なお知らせ」
- ITAKURASTYLE「日経新聞に関する追加」
- ITAKURASTYLE「ミスターマーケットなど短編」
- ITAKURASTYLE「念のため」
- ITAKURASTYLE「カレーとウンコ」
- ITAKURASTYLE「酒は飲んでも呑まれるな」
- ITAKURASTYLE「合宿セミナーランナップ」
- ITAKURASTYLE「呆れます」
- ITAKURASTYLE「足が痛い」
- ITAKURASTYLE「資本主義」
- ITAKURASTYLE「影響はタイムマシーンに乗って」
- ITAKURASTYLE「おいおい間違ってるよ(細野真宏さん)」
- ITAKURASTYLE「コンプライアンス」
- ITAKURASTYLE「サンデープロジェクト」
- ITAKURASTYLE「さよならVOLVO君」
- ITAKURASTYLE「現在の活動の始まり」
- ITAKURASTYLE「失敗から学ぶ」
- ITAKURASTYLE「バレンタインにご提案」
- ITAKURASTYLE「ウォール街」
- ITAKURASTYLE「社会に対する価値提供」
- ITAKURASTYLE「合宿セミナー明け」
- ITAKURASTYLE「居酒屋」
- ITAKURASTYLE「プロフェッショナリズム」
- ITAKURASTYLE「スーパーモーニング出演を終えて」
- ITAKURASTYLE「僕は関係ありません(笑)」
- ITAKURASTYLE「サンデープロジェクト」
- ITAKURASTYLE「鏡」
- ITAKURASTYLE「凄くうれしい講演依頼」
- ITAKURASTYLE「忙しい」
- ITAKURASTYLE「バーゲンセール」
- ITAKURASTYLE「生んでくれてありがとう!」
- ITAKURASTYLE「Merry X'mas!」
- ITAKURASTYLE「わかりやすさの価値」
- ITAKURASTYLE「大失態」
- ITAKURASTYLE「Priceless」
- ITAKURASTYLE「カネ・金・カブ・株・○億円儲ける」
- ITAKURASTYLE「おりおばセミナー祭り」
- ITAKURASTYLE「美人投票」
- ITAKURASTYLE「欠陥マンション」
- ITAKURASTYLE「働くおじさん」
- ITAKURASTYLE「僕の頭を空っぽにしてくれる彼ら」
- ITAKURASTYLE「あれから思うこと」
- ITAKURASTYLE「サプライズ!」
- ITAKURASTYLE「東京湾ナイトクルーズ」
- ITAKURASTYLE「マテ、コノヤロォ~!」
- ITAKURASTYLE「ダイエット」
- ITAKURASTYLE「ネットってすげえ!」
- ITAKURASTYLE「ケータイ・イヤホン」
- ITAKURASTYLE「CDMA1X-WINのデータ通信カード」
- ITAKURASTYLE「ThinkPadその後」
- ITAKURASTYLE「ThinkPadのブルーボタン機能」
- ITAKURASTYLE「外付けHDD買ってきた」
- ITAKURASTYLE「X40 壊れたらしい」
- ITAKURASTYLE「ケータイとイヤホン」
- ITAKURASTYLE「食べ物」
- ITAKURASTYLE「本屋と本」
- ITAKURASTYLE「服」
- ITAKURASTYLE「ゴルフクラブ」
- ITAKURASTYLE「パソコン以外の文房具」
- ITAKURASTYLE「ワイン」
- ITAKURASTYLE「おもてなし」
- ITAKURASTYLE「ホテル(都内)」
- ITAKURASTYLE「カバン」
- ITAKURASTYLE「車」
- ITAKURASTYLE「ケータイ」
- ITAKURASTYLE「ネット接続」
- ITAKURASTYLE「パソコン」
出版物

DVD第2弾「Discounted Cash Flow 入門」

エッセイ集Vol.2 「KISS(=Keep It Simple,Stupid)」
携帯サイトQRコード

http://www.yuichiro-itakura.com/m/